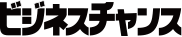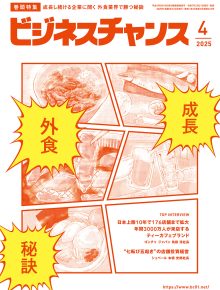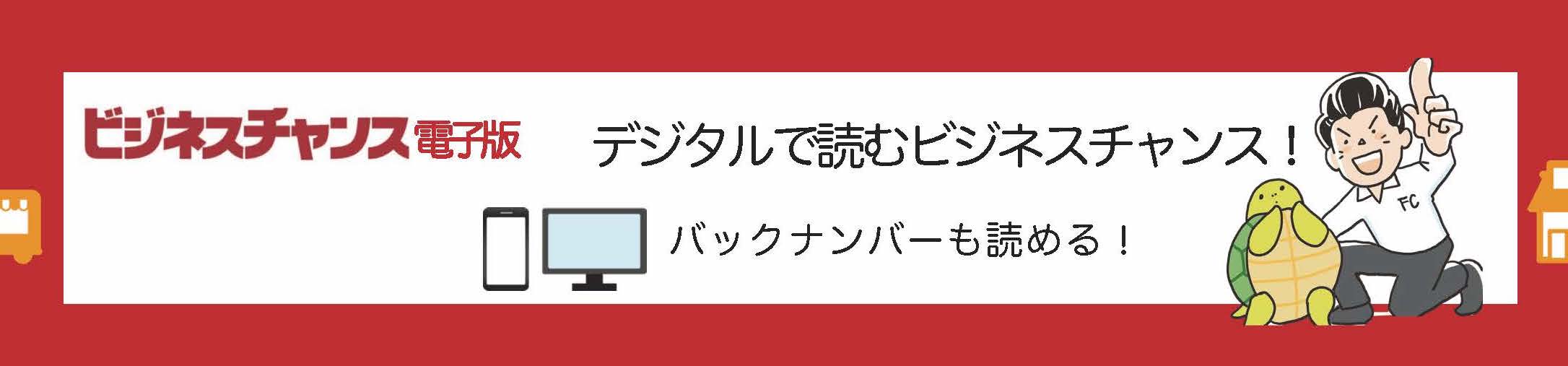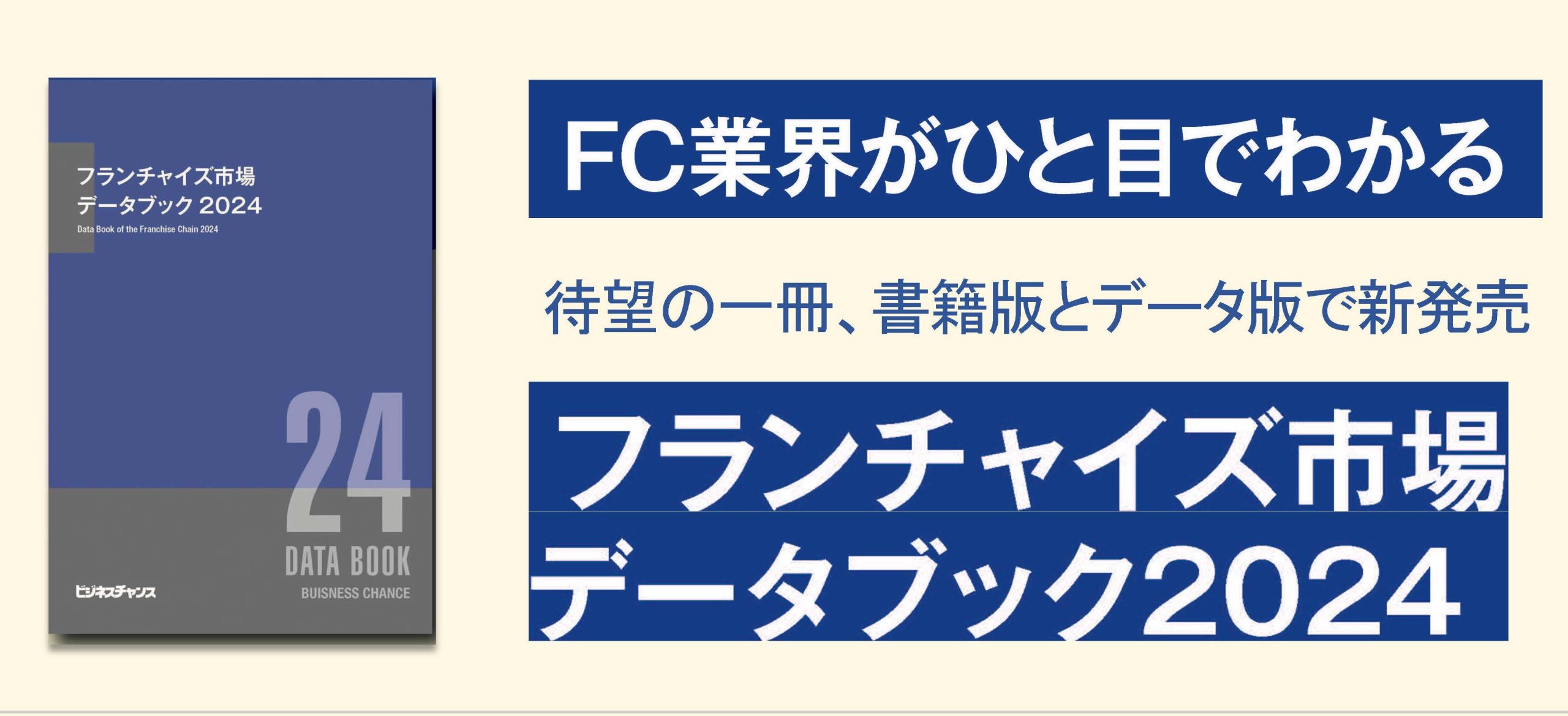【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(前編)
公開日:2025.01.06
最終更新日:2025.04.07
※以下はビジネスチャンス2025年2月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。
独自メニューの開発に注力、20年後の3000店舗を目指す
世界を代表するファストフードチェーン「サブウェイ」の日本事業展開に、外食大手のワタミが乗りだした。同社は2024年10月25日、記者会見を開き、サブウェイの日本法人の買収と国内におけるマスターFC契約の締結を発表した。全国的な居酒屋チェーンで知られるワタミは現在、宅食事業との二本柱経営だが、祖業である外食事業においてはコロナ禍以降、焼肉や寿司、そしてチキンのデリバリーなど多角化を図り、〝脱・居酒屋依存〟を志向してきた。一方、サブウェイは世界で3万7000店舗を展開する一大チェーンだが、日本では上陸して30年が経過したものの、ピークで480店、現在は186店で営業しているに過ぎない。ワタミでは今後10年間で1000店舗、20年後には3000店舗の展開を目指すという。同社の渡邉美樹会長兼社長CEOに、今回の契約に至った経緯と今後の事業展開、そしてその勝算について聞いた。

ワタミ 東京都大田区 サブウェイ、ワタミの宅食、かみむら牧場、から揚げの天才 他 渡邉 美樹会長兼社長 CEO(65)
Profile わたなべ・みき
1959年10月生まれ。神奈川県横浜市出身。「つぼ八」のFC店経営を経て、居酒屋「和民」を開業。参議院議員を務めた後、2019年にワタミ代表取締役会長兼グループCEOとして本格経営復帰。2021年10月ワタミ代表取締役会長兼社長に就任。
コロナ禍をきっかけにファストフードに注目
ワタミはコロナ以降、外食事業における〝脱・居酒屋依存〞経営を推進するべく、焼肉屋の展開などを図る一方、「から揚げの天才」や「bb.q オリーブチキンカフェ」といったデリバリー、さらにはファストフード業態にチャレンジしてきた。そうした中で今回、満を持してスタートしたのがサブウェイ事業だ。駅前やSC、ロードサイドなど、多様な出店形態を持つサブウェイの出店余地は、3000カ所に上るという。
コロナで居酒屋が大打撃 FF業態に活路を見出す
--サブウェイといえば、マクドナルドやケンタッキーなどと並ぶ世界的なファストフードの代表ブランドですが、そもそも御社がファストフードに本格進出しようと考えたのは、やはりコロナ禍がきっかけですか。
渡邉 外食事業はコロナで大打撃を受けて、3日に1店舗閉めている状況でした。これを続けていると会社がなくなってしまうので、何とか店を増やさないといけないと考えました。その中で、「から揚げの天才」や「bb.q オリーブチキンカフェ」など、デリバリー・ファストフードの業態をやったのが一番のきっかけですね。
--まさにそんなタイミングでの今回、サブウェイとのマスターフランチャイズ契約ですが、どのような経緯で契約に至ったのですか。
渡邉 米国ロサンゼルス在住のFCコンサルタントの藤田一郎氏からお話をいただきました。藤田さんとはもともとお付き合いがあり、当社の焼肉事業を海外展開するにあたり、ヒューストンのフランチャイジーをご紹介いただくなど、お世話になっている方です。その藤田さんとお話する中で、サブウェイの米国本部が日本展開を担ってくれる企業を探していると聞きました。
--いつ頃のお話ですか。
渡邉 昨年(2023年)4月ですから、ちょうど1年半くらい前ですね。その話を聞いてからサブウェイにアンテナを立て始めて、日本国内やアメリカなど世界各地に行くたびにサブウェイの店舗をチェックするようになったんです。そうしたら「これいいなぁ。サブウェイしかないな」という風に思い始めて、それで藤田さんにマスター権の交渉をお願いしました。でも、その時には社名を言えばだれでも知っているような大手商社やファミレスなどの有力企業が立候補している状況でした。
--そうした有力企業を抑えるためには、何かアドバンテージになるものが必要だったと思いますが。
渡邉 藤田さんとしては、「確かに今大手との交渉は始まっている。だけど、ワタミさんは有機野菜を持っているから非常にアドバンテージがある。それから、同じ米国本部のTGIフライデーズの日本展開を25年やってきた。その実績は大きい」と言ってくれたわけです。アメリカの本社も「日本はワタミがいいかもしれない」ってことで傾き始めて、そこから1年ですよね。
--その後はトントン拍子でしたか。
渡邉 サブウェイの本社は大企業ですから、それこそ契約書の一言一句からチェックが厳しかった。しかし、中国は3年かかったと言いますから、日本はまだ早かった。それでも1年はかかりましたね。
10年で1000店舗 出店余地は3000カ所
--現在、サブウェイはFCのみで国内に約180店舗を展開していますが、今後の出店計画は。
渡邉 契約上は年間で直営125店、FC125店の合計250店舗となっています。しかし、私たちの目算としては年で1000店舗に持っていこうと。その中身として、直営を毎年店舗出して年で130店舗。残り870店舗がFCとなるわけですが、すでに約180店舗が出店済みなので、あとは約690店舗です。
--駅前やSC、ロードサイドなど、さまざまな出店形態が考えられますが、出店余地はどれくらいを見込んでいますか。
渡邉 現在、国内にサブウェイが出店できるようなモールが3000カ所あります。そのうち4割の1200カ所は出店可能だと見ています。また、駅前は乗降者数4万人くらいのところでいけるだろうと考えていまして、それが約700カ所。そしてロードサイドが1000カ所。あと100カ所は大学や病院の敷地内になります。これを全部合わせると3000までは持っていけると目算しています。
--新規出店開始はいつ頃になりますか。
渡邉 来年(2025年)2月下旬に旗艦店を出す予定です。来年は35店舗、再来年は50店舗、その後は毎年100店舗ペースで出店し、10年で1000店舗を目標にしています。
--優先的に出店するエリアは。
渡邉 最初は東京を中心とした首都圏で、駅前とモールでドミナントを組んで展開する考えです。ロードサイドはその後ですね。

今後はメニュー開発に注力し、夜売上拡充を狙う
「サブウェイ」の日本におけるこれまでの事業展開
サブウェイは1965年に米国コネチカット州で創業。その後、世界でFC展開を進め、日本では1992年、サントリーがマスターFC契約を締結。日本における事業パートナーとして店舗展開を図ってきた。2014年にはピークとなる480店まで店を増やしたが経営は安定せず、2018年にはサントリーが事業から撤退。以後は本国直轄による日本法人が経営を担当しているが、その際にFC店を残してすべての直営店を閉店したため、国内店舗は180店まで減少した。「野菜のサブウェイ」などのブランド推進で健康志向の女性などにファンがいるものの、他の大手ファストフードと比べても店舗数が少なく存在感は薄かった。今後、ワタミが経営テコ入れに乗り出したことで、どう変わるかが注目されている。
投資収益率高く3年で資金回収も可能
サブウェイはほかの飲食店やファストフード店と比べて厨房設備が少なく、小さなスペースでも開業できるのが強みだ。コンパクトな店舗では初期投資が約2000万円で済むため、これまでは個人オーナーも多数加盟している。ビジネスモデルは月商600万円、年商7000万円に対して営業利益7%、年間資本3回転でROI(投資収益率)21%が見込まれ、投資回収期間は3年となっている。
2000万円から開業可能 投資回収は3年を見込む
--サブウェイは、ほかの外食ブランドと比較して小さなスペースで開業できることが魅力の一つです。
渡邉 6.5坪で開業できます。また、機械化を含めて出店や運営に関するシステムができあがっていることも大きいと思います。
--大体、初期投資はどのくらいを考えたらよいですか。
渡邉 目安は2000万円です。これは先ほど言った6.5坪スペースの場合ですね。フードコートに8坪で開業する場合は2580万円です。
--比較的投資額が低いため、個人の方でも加盟できそうです。2000万円で開業した場合、月商はどのくらいですか。
渡邉 6000万円です。ですので、資本回転は2000万円に対して年商7000万円で年3回転が一つの目途ですね。
--オーナーの手残りはどうですか。
渡邉 そんなに手残りが多いビジネスではありません。というのもロイヤリティが8%ですから。それに広告宣伝費として3.5%をいただきますので。ただ、営業利益率7%と年間資本3回転がほぼ確定しているため、7%×3でROIは21%。ROI21%ならば3年で投資回収できますから、ビジネスとしては面白いのではないかと思います。

【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(中編)
【ワタミ】脱・居酒屋依存を図るワタミが日本サブウェイを買収(後編)
次なる成長を目指す
すべての経営者を応援する
フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。
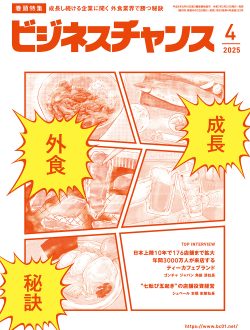
次号発売のお知らせ
2025年8月21日発売
記事アクセスランキング
次なる成長を担うすべての起業家を応援する
起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。
すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。
資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。
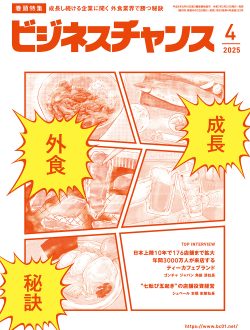


 人気のタグから探す
人気のタグから探す