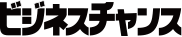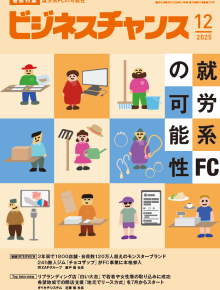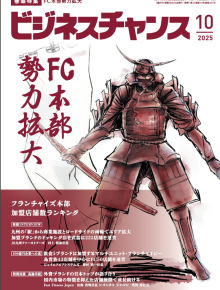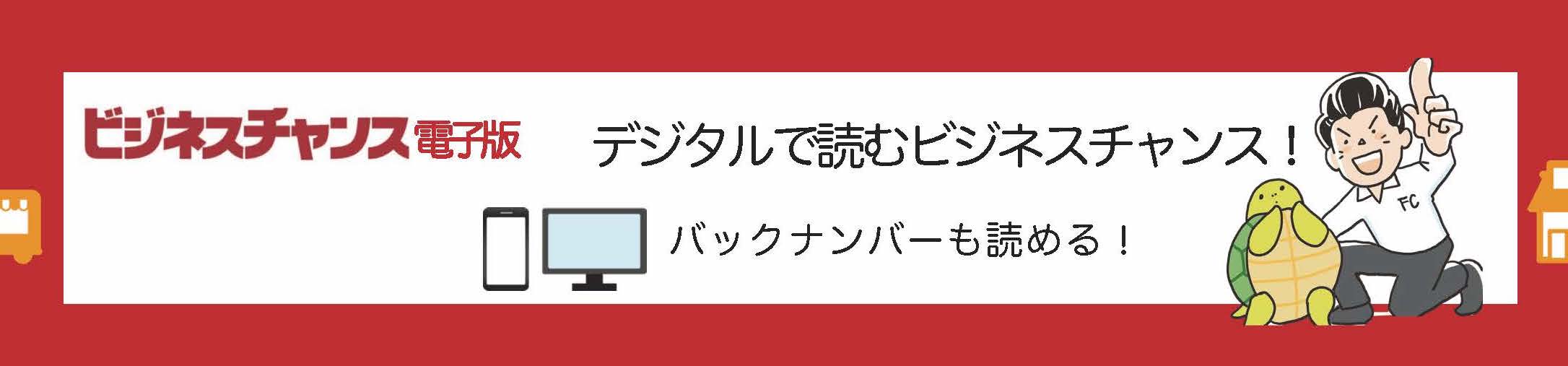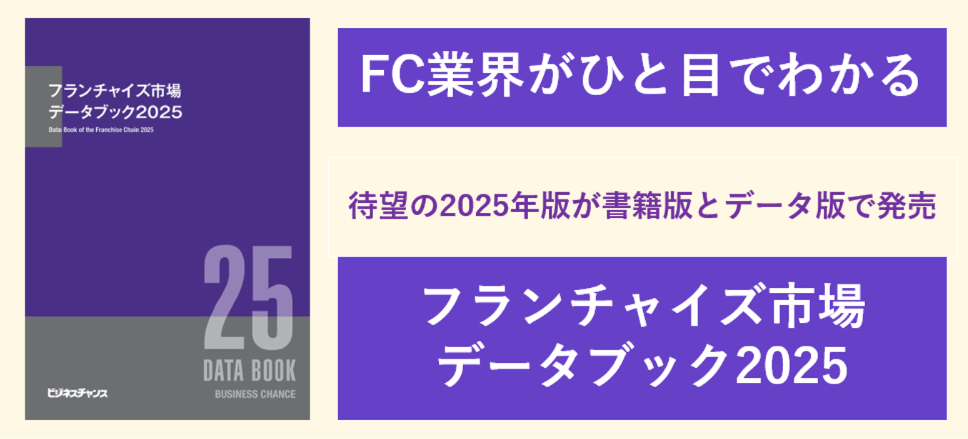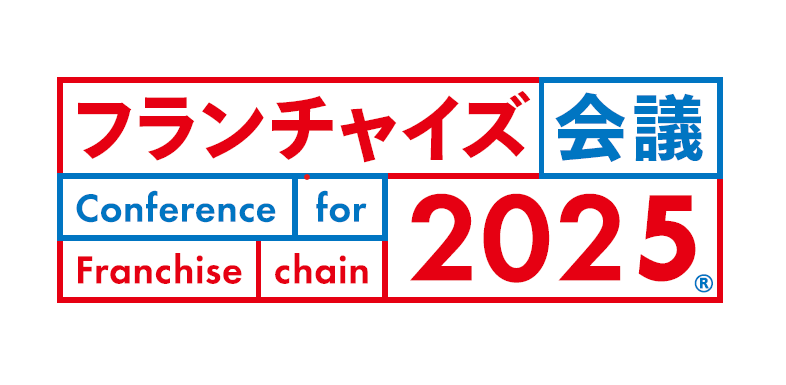【大宮電化】ドミナント戦略で埼玉中心に66店舗を出店
公開日:2025.04.23
最終更新日:2025.07.02
※以下はビジネスチャンス2025年6月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。
隣接エリアにも進出し、5年後に100店舗を目指す
大宮電化は、埼玉県を中心に「ハードオフ」「オフハウス」などのFC店を66店舗展開するメガフランチャイジー企業だ。全国に36社を擁するハードオフグループのFC企業の中でも5本の指に入る有力企業で、25年2月期の年商は42億円を見込んでいる。今後は東京、千葉などの近隣エリアへの出店も行い、2030年に100店舗、年商70億円を目指している。
埼玉県下でドミナント出店
同社はハードオフを中心に、オフハウス、ホビーオフ、モードオフなどハードオフコーポレーションが展開するFCブランドで、64店舗を出店している。本社のある大宮を中心に、北は東北線沿いに久喜・加須方面と、高崎線は上尾・鴻巣方面に。東は春日部・越谷、南は川口・戸田、そして西は川越・坂戸。県西郡部のエリアを除く、県内の主要エリアをほぼ網羅する形で店舗展開している。現在は東京・千葉にも各1店舗を出店済みだ。
最も店舗面積が大きいのは、坂戸店で約600坪。次いで鴻巣店が500坪だ。このほか2階建ての旗艦店である春日部4号店も500坪、また久喜店は270坪だったが、改修して400坪に拡張した。売上は久喜店と坂戸店が2本柱でそれぞれ年間3億円。その後に鴻巣店、上尾本町、春日部4号店が2億円で続く。
「当社はこれまで埼玉県を中心としたドミナント戦略により出店を続けてまいりましたが、正直、古いお店は小規模店舗も多く、効率は悪くなっています。そこで最近は小規模店舗を統合して大型化を図ってきました。また、埼玉県内の出店には一定の飽和感がありますので、今後は東京、千葉にもさらに出店エリアを拡大していくつもりです」(青木義宏社長)
同社ではまた、一部の店舗に併設する形で100均のダイソーFCにも加盟しており、現在2店舗を運営する。
2025年2月期の売上高は、ハードオフ事業が64店舗で40億円、これにダイソーの2店舗を足して合計42億円を見込んでいるという。

約600坪の最大面積を有する「坂戸店」
バブル崩壊で状況一変
同社は、1959年に青木義宏社長の父親で現会長の青木義雄氏が23歳の若さで創業。2年後に大宮電化販売を設立した。東京オリンピックを控えた1964年には売場面積38坪と、当時では県内最大級の大型店を出店。1965年には社員14人を数え、売上高は1億円に到達。高度経済成長期にはテレビやエアコンが爆発的に売れ、店舗網を拡大していったという。
「1980年には売上高が10億円を超えるまで成長しました。その後も順調に出店を続けましたが、1990年代初頭にバブル経済が崩壊。その結果、16店舗で社員数130人、売上高約50億円をピークに売上は急落して、1993年には売上高がピーク時の約2分の1まで激減し、大幅な赤字に転落。もう潰れる寸前ですよね。しかし、幸いなことに借入が少なかった。というのも会長は若い頃、エアコンの大量仕入れをした年が冷夏となり、本当に資金繰りで自殺しようかというくらい追い込まれたことがありました。以来、無借金を心掛けており、これで助かったのです」(青木社長)
1994年には、大手家電量販店ケーズデンキのFCに加盟。売上は一時的に回復したものの、本部から不採算小型店の閉店と大型店の出店の要請があった。しかし、大型店を出店すれば借入や固定費が膨らむため、大型店の出店は決断できずにいた。小型店を閉店した結果、再度赤字に転落してしまった。
「そんな折、1999年に会長(当時社長)が家電メーカーの販売会社担当者から、新潟でリユース業に転換して成功している会社があるという話を聞いたそうです。それがきっかけとなり、ハードオフコーポレーションの創業者である山本善政社長(当時:現会長)を紹介していただきました。面会した会長は、リユースビジネスに強い魅力を感じ、その場でFC加盟を決断。同年8月に『ハードオフ羽生店』を出店したのです」(青木社長)
結果、5年間継続した家電量販店FCからは脱退。家電販売からリユースへ完全に事業転換する再スタートを切ったという。

1964年に開業した大宮電化販売本店
本業転換と代替わり
ハードオフの出店地域は、既存店を中心とする10万人商圏が、新店候補地を中心とする10万人商圏と重ならないというルールがある。同社は埼玉県内で家電販売店を出店していたこともあり、既存の家電店をリユース店に転換させることから始めた。しかし、リユース店に転換するには100坪以上の店舗面積と10台以上の駐車場が必要だ。
大手家電量販店のFCを撤退した時、10店舗が残っていた。しかし、この条件を満たさない店舗もあったため、すべての家電店をリユース店に転換させることはできず、結果として4店舗を閉めて6店舗で業態転換を図った。
「当時、家電の店舗は50坪や60坪とか、そういう店ばっかり。ハードオフをやるには小さすぎた。それでもなんとか切り替えて、6店舗で再スタートをしたものの、『リユースなんてやりたくない』と社員が半分くらい辞めてしまって、当時は大変だったようです」(青木社長)
同社にとってリユース業界は厳しい船出となったが、残った社員たちの奮闘もあり、その後は徐々に売り上げを伸ばして黒字化も実現した。1号店の出店から翌年の2000年までに10店舗を出店した。新規出店の基本方針は、埼玉県内で鉄道や幹線道路沿いの人口が多い地域を中心とすること。徐々に隣接地域に拡大するドミナント戦略を採用した。また、新規出店と並行して積極的に人材採用も行った。
その結果、2003年までに小型店を中心に20店舗、その後は店舗面積400坪以上の大型店の出店にも着手し、2010年には30店舗にまで店を増やした。
青木社長が同社に入社したのはその頃だった。それまでは23年間、銀行に勤務。仕事が楽しくて跡を継ぐ気はなかったという。しかし、状況が一変したのは2008年だ。父親で当時、経営のすべてを取り仕切っていた義雄氏が重篤な病気で突然倒れてしまったのだ。幸い、近所に大きな病院があり、夜中に緊急手術を行えたことで一命を取り留めた。
「当時は30店舗ほどあって、従業員も300人以上いたと思います。母は手伝っていましたが、そのほかに親族は会社にいませんでした。もし父がいなくなったら、どうなってしまうのか。その時、はじめて真剣に考えました」(青木社長)
銀行を辞めて大宮電化に入社するや、一番大きな店舗に入り、新入社員と同じように買い取りや販売のオペレーションを学んだ。幸いにしてその後も順調に出店ペースは伸びて、2014年までに40店舗、2016年までに50店舗と拡大。その間の2015年に義宏氏は社長に就任した。
社内改革
青木社長の社長就任以降もさらに順調に出店数を伸ばし、2020年には60店舗を超えていたが、その裏ではさまざまな社内改革を断行してきた。
最初に着手したのが社内コンプライアンスだ。青木社長が就任した時、残業代の支払い問題に対応した。目先の問題を解決すると共に、深夜残業はさせないという基本方針を盛り込んだ就業規則に変更。次いで、新卒採用を開始した。
「それまでは中途採用が中心でしたが、さらに新店を出すなら新卒採用は必須です。結構いい人材が入社するようになりました。しかし、有名大学卒の社員が入社するようになっても、離職率は下がりませんでした。有能な人材を採用しても、条件のよい企業に転職していく。その流れを止められずにいたのです」(青木社長)
また2020年にコロナが発生すると、店舗の休業や営業時間の短縮を求める社員やパートタイマーが続出、従業員の離職も増加した。こうした従業員の動きに対して、同社は労務問題に詳しい専門家に相談。離職率を改善するために待遇改善にも着手した。ハードオフの営業時間は10時開店で20時閉店だが、同社は10時30分開店で19時30分閉店と、営業時間を1時間短縮した。このほか、経営に影響が出ない範囲で給料も引き上げた。
「従業員からは毎年のベースアップに加えて、業績に応じた特別賞与の支給、役職手当、家族手当、通勤手当の増額、休日の増加、定年延長などの要求がありました。話し合いの結果、従業員たちの待遇は良くなりましたし、さらに従業員の健康管理の重要性に注目し、対策を行ってきました。結果、経済産業省が認定する健康経営優良法人に2022年から毎年認定されています。今では離職率は下がり、社員・スタッフのモチベーションがアップし、結果として業績も改善しました」(青木社長)
一方、社員育成において、本部による研修だけでなく、独自研修にも注力している。同社は出店エリアを6エリアに分類しており、研修内容は各エリアの責任者である6人のエリア長が考案する。新入社員研修に加えて、若手社員を店長にするための育成研修や新卒社員のフォローアップ研修、経験が浅い店長向けの業績アップ研修、商品知識をアップデートする研修などを行っている。そのほか、隣接する他社のハードオフ加盟店と店長を交換するトレード研修も実施。研修期間は1日だが、互いに他社の良い部分を学ぶ目的で定期的に行っているという。
「はじめのうちはコストばかりかかり、研修の効果に疑問を感じていました。しかし、研修後の報告書を読むと、悩みを抱えていた若手に自信がついた、人が変わったように動くようになったとありました。これは業績アップにつながっていることに間違いはありません。ですから今は、やりたいという研修はやらせるようにしています」(青木社長)

本部研修以外に自社独自の研修にも注力
ハードオフチェーンの強み
父親の後を継いで社長に就任し、今年で丸10年。この間、ハードオフの本部経営陣やFC加盟店の経営者仲間とも交流を深めていく中で、青木社長はハードオフの経営のあり方に強い信頼感を抱くようになったという。
「ハードオフ事業に最も力を入れているのは、業界自体の成長性や将来性が高いこともありますが、経営理念が確立していることが一番です。毎日、全店舗の朝礼でハードオフの経営理念を復唱しています。採用面接の際にも、『どうして当社に入社しようと思ったのですか』と聞くと、多くの人が『理念が素晴らしい』と答えます」(青木社長)
金儲けや売上を追わないというハードオフコーポレーションの山本会長のブレない姿勢が加盟各社の経営者だけでなく、従業員にも支持されているのだろう。
ハードオフは、加盟企業の健全な経営に基づく協働事業を重視している。そうした企業姿勢を最も象徴しているのが、加盟店の新規オープン時に恒例となっている応援だという。
「新店がオープンする時は、前日から他のFCオーナーも駆けつけて前夜祭をやるんです。さらにそれが終わった後も、ホテルの部屋に集まって情報交換したり、身の上話をしたり(笑)。だから、すごく仲がいいですね」(青木社長)
グループの情報共有も強化されている。本部は営業管理システム「ReNK BASE」を独自開発。パソコンと連携し、買取や売上といった営業情報をグループ内で共有できるようになった。
同社はこれまで独自にシステムを組み、全店舗の商品管理をはじめ、経理処理を行ってきた。しかし、本部が「ReNK BASE」を開発・導入したことで、こちらへの切り替えを進めている。同社では2023年から2年かけて全店舗に新システムを導入した。
ReNK BASEは社内システムとの連携に課題はあるものの、ECサイトには非常に優れているという。同システムをタブレットに導入することで、タブレットで商品を買い取れるようになった。また、タブレットで商品撮影し、そのままECサイトにデータを移すことができる。商品の買取からECサイトへのアップまでタブレット1つでできるため、ECの売上が全体の約10%を占めるようになった。
現在、ハードオフグループ全体でEC売上は平均10%にまで伸びてきている。大宮電化でも同システムの全店舗導入が完了して、すぐにグループ平均に追いついた。
今後の戦略・課題
今後も同社は、継続的な出店を続け、成長を図る計画だ。しかし、店舗数が増えるにつれ、近隣の直営店や他のFC加盟会社の店舗と商圏が干渉するようになり、出店速度が遅くなる傾向が現れはじめた。
これを踏まえ、青木社長は前述の通り、小型店の統合を検討している。同社にはまだ100坪前後の小型店が多くある。そこに従業員を2〜3人配置するのは非効率であり、社内の隣の店舗と競合するからだ。
「たとえば800坪の店舗があったとして、ハードオフとオフハウス、ホビーオフを入れた複合店にします。それでも使いきれない場合は200坪をダイソーに割り当ててもいいかもしれません」(青木社長)
また、在庫回転率の改善も今後の大きなテーマだという。
「買い取りは旺盛ですが、果たして価値に見合った買い取りをしていたかというのは疑問です。結果、在庫が膨れ上がり長期滞留の在庫が増えていました。他社のバランスシートを見る機会があったのですが、当社は在庫が過剰だなと感じました。もっとキャッシュフローを重視した買い取りにしないといけない。こうしたことから、人事評価も変えました。利益よりキャッシュフロー重視に切り替えたのです」(青木社長)
現在はハードオフ事業の売上億円に対して、在庫は約11億円。在庫回転率は3.6回転となり、同社ではこれを5回転するまでに持っていきたいという。
「何でも買い取るといったやり方は止めました。結果、最近では無駄な買い取りがだいぶ減りました。在庫が増えるとキャッシュがどんどん出ていくだけですからね。在庫は怖いですよね。そこはちょっと抑制をかけようと。その代わり、いいものを買い取る。そうすればECでも全国の消費者に売ることができます」(青木社長)
同社は今後、小型店舗を統合して大型化を図る一方で、東京都や千葉県などの近隣地域への出店エリア拡大にも挑戦する。2030年前後には100店舗、年商70億円を目標に据える。

家電販売店(左)からのちに増築した「旧ハードオ フ・オフハウス久喜店」(上)。その後昨年1月にリニュー アルオープンした(右)
会社概要
代表者 青木義宏
所在地 埼玉県さいたま市
設 立 1976年
所在地 5000万円
年 商 38億5900万円(2024年2月期決算)
店舗内容
ハードオフ:埼玉県(31店舗)オフハウス:埼玉県(29店舗)・千葉県(1店舗)
ホビーオフ:埼玉県(2店舗)モードオフ:東京都(1店舗)ダイソー:埼玉県(2店舗)
 大宮電化(埼玉県さいたま市)
大宮電化(埼玉県さいたま市)
青木 義宏社長(62)
1962年埼玉県生まれ。早稲田大学商学部卒業。 87年に住友銀行(現:三井住友銀行)入行。支店にて融資業務、格付機関にてアナリスト業務を経験。その後、銀行本部で起債推進業務や政策投資審査業務、ベンチャーキャピタルにて未上場株式投資業務、不動産アセットマネジメント会社で不動産ファンド組成業務に携わる。その後、不動産投資信託運用会社にて取締役財務部長等の経験を経て、2010年に大宮電化常務取締役。15年に代表取締役社長に就任。
次なる成長を目指す
すべての経営者を応援する
フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。
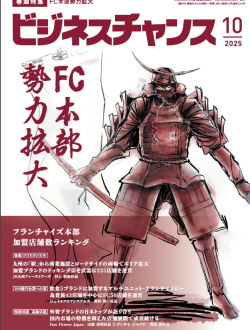
次号発売のお知らせ
2026年2月24日発売
記事アクセスランキング
次なる成長を担うすべての起業家を応援する
起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。
すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。
資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。
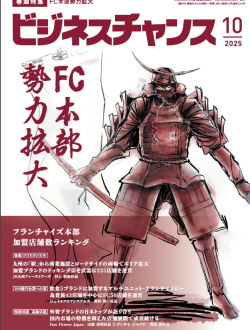


 人気のタグから探す
人気のタグから探す