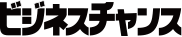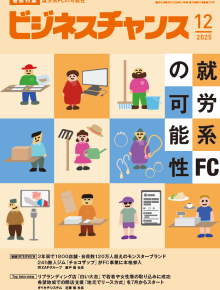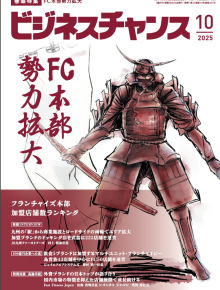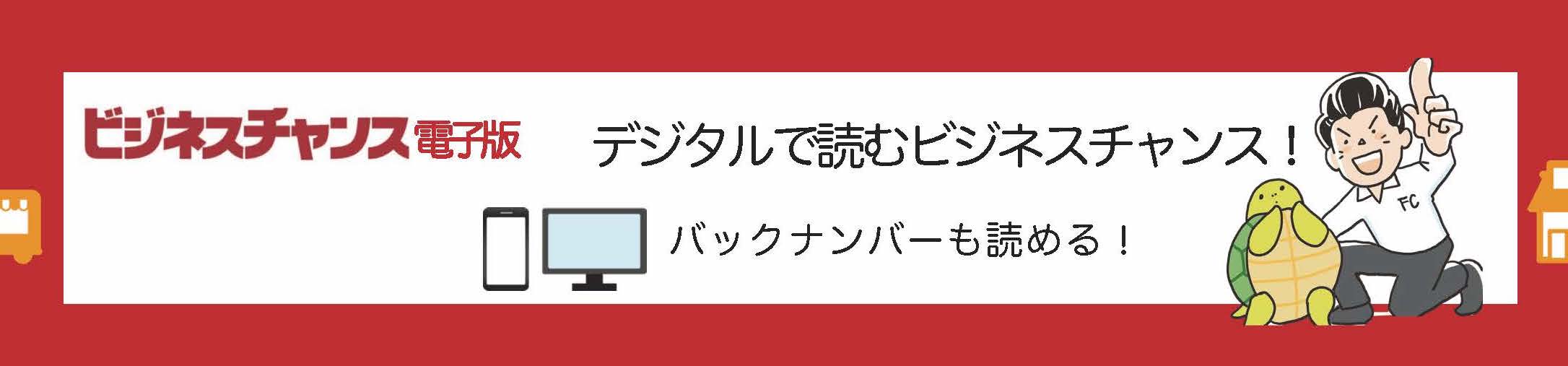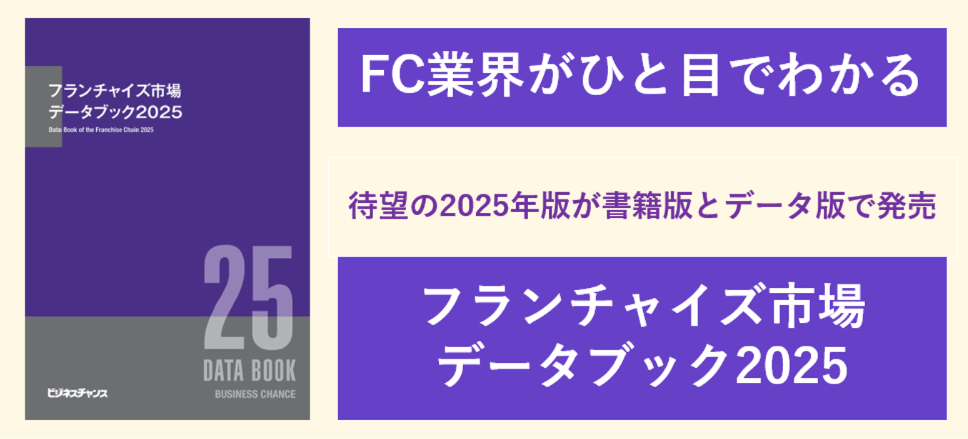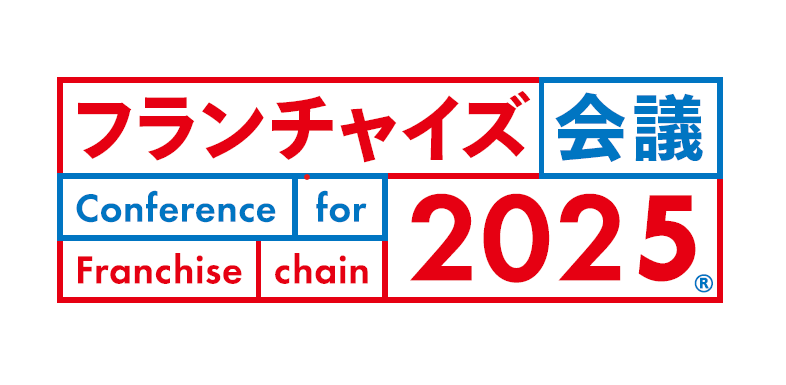【識者が解説】「フランチャイズは地方を救うか」
公開日:2025.07.20
最終更新日:2025.07.20
※以下はビジネスチャンス2025年8月号から抜粋した記事で、内容は取材時の情報です。
FCの地方進出による雇用創出と事業者輩出の可能性
FC加盟のメリットの1つは、持続的に運営できるように作り込まれたノウハウがもたらされること。ロイヤリティなどの対価を支払えば、知名度の高い看板や効率化されたオペレーションが手に入り、商品供給や継続的な支援も受けられる。この仕組みを地方創生に活かすために活動しているのが、関西学院大学名誉教授の川端基夫氏だ。今回は、FCの社会的意義と地方FCの課題について聞いた。
FCの捉え方の違い 地方にとっては有名店
--近年のフランチャイジーの兆候をどう見られていますか。
川端 私は、「日本の法人フランチャイジー」(2021年/新評論)という本を出すにあたり、約2年かけて全国のフランチャイジー78社を回りました。その中で、大都市のメガジー社長と地方のメガジー社長で加盟に対する考え方が異なる点に気づきました。
大都市で、特に兼業型でFCを運営する社長はもう1つの収益事業が欲しいという思いが非常に強い。そうなると、投資効率やブランド競争力という観点で本部を選ぶことになります。一方、地方のメガジーは地元で何代にも渡って本業を営み、商工会の会長をやっているなど、地元の名士であるケースが多いです。そのため、利益よりも地元の人が喜ぶか、地元の活性化に繫がるかを軸にブランドを選ぶ傾向があります。
--大都市と地方で加盟動機が異なる理由について、どのように考えていますか。
川端 FCであるかは別として、チェーン店についての捉え方が大都市の住民と地方の住民でだいぶ違うのだと思います。大都市の住民からすると、チェーン店は個性がなくて面白くない。飲食であれば、個人経営の個性的なお店に入りたいと思います。一方、地方の住民にとってチェーン店は有名なお店です。都市で流行りのお店に入りたいというニーズが一定数あります。そこから、地方のメガジーは加盟に際して、地元の人のニーズや憧れを反映するという発想になります。
--そう考えると、地方におけるFCの役割は非常に大きいです。
川端 FCの仕組みは、地方の課題を解決するにはもってこいのシステムだと思います。FCのメリットの1つは、チェーンマネジメントにおいて作り込まれたノウハウをもたらしてくれることです。飲食のFCに加盟すれば毎朝食材は届きますし、定期的に新メニューも提供できます。もちろん、地方でも個人店を開業できますが、人も支援も少なく、仕入れも難しいです。そのため、持続可能性という観点で捉えると、FCは地方でこそ高い有効性を発揮するシステムだと言えます。
--地方にFCを取り入れた場合、雇用創出にも繫がります。
川端 FC出店があれば雇用が発生するため、地方の貴重な働き口となります。加えて、FCの場合は収益がオーナーの手元に残るため地元でお金が循環します。さらに、地方自治体から見ると税収の増加にも繫がります。
また、FCオーナーの中にはある程度マネジメントが身に付くと、別の事業に挑戦される方もいます。つまり、FCは地方で事業家が育つ可能性を秘めているのです。事業家がいて、人を雇って、税金を払う。こうしたお金と人の循環が地域の自立に繫がります。これこそ、地方創生のど真ん中だと考えます。
損益分岐の壁で浸透せず地方型モデルの開発が急務
--FCは地方創生にとって有効な手段にも関わらず、それほど浸透していません。
川端 今はどこのチェーンもFCパッケージが1つしかありません。青森や鹿児島でも東京と同じ契約をしています。大体のFCパッケージは都市部の市場をベースにした設計になっているため、地方で展開するとなると損益分岐のハードルがあります。たとえば、高齢者向けの配食サービスの場合は1日当たり最低でも200食の注文がないと成り立たない設計になっているわけです。それを150食でも成り立つように、契約内容やロジスティクスのシステム、店舗設計や商品構成などを工夫し、損益分岐点を下げた「地方型モデル」を開発する必要があります。
また、すでにコンビニFCでは実施されていますが、年齢条件の引き上げも必要です。65歳で定年退職し、田舎の親の面倒を見るために帰郷する人が一定数いる中、田舎には仕事ができる環境がありません。FCの年齢条件の引き上げにより、その人たちが仕事できるようになると人口移動にも繫がります。
--地方モデルを作れば市場がさらに広がります。
川端 ただ、FCは品揃えやメニュー、値段や内装、看板などが全て統一されていることに価値があると思われてきました。しかし、ガソリンスタンドなど代理店型の商売の場合は、「エネオス鈴木燃料店」というように販売店の名前が出ています。誰が運営しているのか分かる方が、地元の人は安心しますよね。そのためFCだから全部統一という考えは、地方の視点から見たときに合致しているのかという問題があります。
--確かに、同じブランドでも都市部と地方で利用のされ方が異なります。
川端 某定食屋FCに加盟している広島のフランチャイジーから聞いた話ですが、同ブランドは都市部でサラリーマンやOLが1~2人でお昼時か仕事終わりに来ることを想定して作られています。それを広島の田舎で出店したとき、親子三世代で来るケースが結構あるそうです。地方で外食といっても選択肢が少ないため、ご高齢向けの焼き魚定食や子ども向けのハンバーグまで幅広いメニューを揃える定食屋は貴重ですから。しかし、せっかく三世代で来店されても座敷席がなく、大人数に対応できる店の造りになっていません。これを本部にリクエストしても、なかなか対応できないのが現状です。
--地方でFCが浸透するには地方モデルの開発に加え、どのような取り組みが必要でしょうか。
川端 FCの社会的意義を正しく評価する必要があると思います。今、地方が抱える1番の問題は生活インフラが決定的に欠乏していることです。食料品を買うにも不便ですし、高齢者向けサービスも行き届いていません。地方で暮らし続けるためには、やはりFCの仕組みを上手く使って生活インフラを整備することが重要だと私は思っています。
とはいえ、FCは訴訟問題などでマイナスのイメージもあるため、地方の人の中にはFCが進出することを毛嫌いする人もいます。そこで、私が所属する日本マーケティング学会のフランチャイズ・システム研究会では、「フランチャイズは地方を救うか」というテーマの共同研究を5月に発足させ、客観的な視点からFCの地方での可能性と課題を研究することにしました。これに必要な研究費は、今年の6月4日から7月末までの期間にクラウドファンディングで集めます。
--FCのイメージアップに期待がかかる研究です。
川端 これまで、FCの社会的意義に関する議論はほとんどなく、防犯や防災の観点でコンビニがスポットを浴びる程度でした。しかし、この研究が進めば、コンビニ以外のFCの社会的意義も示すことができ、ひいてはFCが地方創生に寄与する存在であることが実証できるでしょう。さらには、来るべき人口減少時代のFC事業のあり方も示せます。
共同研究
「フランチャイズは地方を救うか」の研究費を募るクラウドファンディングのページ
 関西学院大学名誉教授
関西学院大学名誉教授
川端 基夫 氏(69)
プロフィール:(かわばた もとお) 1956年生まれ。関西学院大学名誉教授、博士(経済学)。流通業の国際化、フランチャイズ論が専門。日本商業学会理事、日本マーケティング学会理事。著書「日本企業の国際フランチャイジング」(2010)、「外食国際化のダイナミズム」(2016)、「日本の法人フランチャイジー」(2021)など多数。
次なる成長を目指す
すべての経営者を応援する
フランチャイズ業界の専門情報誌

フランチャイズ業界唯一の専門情報誌として、毎号さまざまな切り口をもとに新興本部から大手本部までをフォーカス。またFCを自社の新たな経営戦略として位置付け、中長期的な経営を目指す経営層に向け、メガフランチャイジーの情報も提供しています。
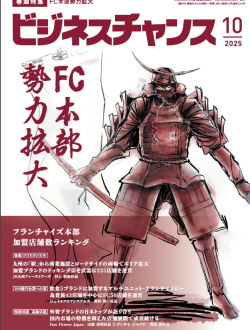
次号発売のお知らせ
2026年2月24日発売
記事アクセスランキング
次なる成長を担うすべての起業家を応援する
起業&新規事業の専門情報誌

“起業のヒント” が毎号充実! “ビジネスチャンス” の宝庫です。
すぐにでも役立つ独業・開業・転業・副業サポートの雑誌です。
資金をかけずに始められる新しいビジネスの紹介、FC、経営・会社運営のノウハウなど、多くの経営者からの“起業のヒント”が毎号充実。
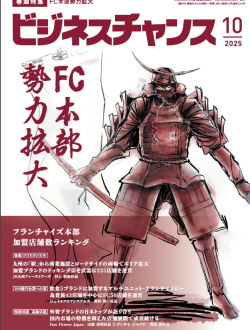


 人気のタグから探す
人気のタグから探す